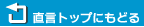|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|||
|
|
|
|
|
現実と理想 「曲学阿世の徒」のいない春 |
理想語る気概、自信なし 「曲学阿世」 という言葉は、「史記」 の 「儒林列伝」 の中にある。その意味は、「真理にそむいて時代の好みにおもねり、世間の人に気に入られるような説を唱えること」 (大字林) である。 この言葉が、世間の耳目を集めたのは、戦後間もない1950年5月、当時の内閣総理大臣吉田茂が自由党の両院議員総会秘密会で、「永世中立とか全面講和などということは、言うべくしてとうてい行われないことであるが、それを南原繁東大総長などが政治家の領域に立ち入ってかれこれいうことは、曲学阿世の徒にほかならない」 と演説したのが、後刻大きく取り上げられ、国論を二分する大論争となったからであった。 他方、こう難詰された南原学長も負けてはいない。「複雑に変化する国際情勢の中にあって、現実を理想に近接融合せしめるために、英知と努力をかたむけることこそ、政治と政治家の任務であるにもかかわらず、『曲学阿世の徒』 の空論として、全面講和や永世中立論を封じ去ろうとするところに、日本の民主政治の危機の問題がある」と難じたのである。 この論争については少し解説しておく必要がある。この時代、世界には、米国を中心とする西側陣営と、ソ連を盟主とする東側陣営が、激しく対立する東西冷戦構造がすでにでき上がっていた。この2年前には、ベルリン封鎖で東西危機が増し、この翌月には朝鮮半島で熱戦の火蓋(ひぶた)すら切って落とされた。そんな厳しい現実を前に、日本はあの 「十五年戦争」 を清算し、独立国家として世界と講和を結ぶことが求められていた。 この講和を全世界との和解の機会とするのか、アメリカおよびその陣営に属する国家とだけ和を取り結ぶのか、両論が激しく争われていた。前者を 「全面講和」、後者を 「単独講和」 と呼んだ。そして、南原繁らの政治学者や文化人、日教組など労働団体、左翼政党などは 「全面講和」 や 「非武装中立」 を、自由党など政権中枢は米国を中心とした単独講和を主張し、両派は真っ向から対立したのである。 こんな中、佐藤栄作自由党幹事長は、「自由党は政治的観点から現実的な問題として講和問題を取り上げているのであって、これは南原氏などにとやかく言われるところではない。もとよりこの問題はすでに政治の問題になっているので、象牙の塔にある南原氏が政治的表現をするのは日本にとって百害あって一利無しである」 と論難した。 翌年9月4日からサンフランシスコで開かれた対日講和会議が、東側陣営を除いた片面講和となったのは、歴史年表にあるとおりである。これを機にわが国は、日米安保体制と再軍備を認めることで、生まれたばかりの 「理想」 主義という赤子をたらいの水と一緒に流し去ったのである。 こんな古い話を持ち出したのは他でもない。戦後のこの時代にはまだ、「現実」 が 「理想」 という言葉の反意語として通用していたということを思い出したかったからだ。 いま、「現実」 の反対は何かと問われて、もはや 「理想」 などとは答えられまい。これに代って 「虚構」 あるいは 「仮想現実 (バーチャルリアリティ)」 などがその位置を占めているのではないか? 「ニート」 と呼ばれる若者達は、額に汗する労働とは無縁な仮想現実の中に生きている。答弁に窮すると 「人生いろいろ」 とうそぶく内閣総理大臣、引責辞任後もなお影響力を画策する大マスコミの巨魁(きょかい)、無能を恥じない各界・各層のリーダー達。いずれも、「虚構」 のなかにその地位を占めていないか。空中浮遊を標榜する宗教団体、カリスマ予言者に、振り込め詐欺の悪党どもまで、世は 「非理想」 にあふれかえっている。 「再び子供を戦場に送るな」を合言葉に、戦後一貫して非武装・中立の 「理想」 の旗を掲げ続けた山教組までが、政治と金の悪習に巻き込まれていたという。そこには善悪を峻別(しゅんべつ)し、「理想」 を語る気概や自信は微塵(みじん)も感じられない。この国では、もはや 「理想」 という夢を語る 「曲学阿世の徒」 すら絶滅したのであろう。 |
|