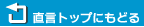|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|||
|
|
|
|
|
社会の常識 国民を愚弄した増税論議 |
説明責任果たし、展望示せ 総選挙が終わったら、まるで示し合わせていたかのように、各方面から増税論議が起きてきた。所得税の定率減税の縮小・撤廃をはじめとしてサラリーマンの懐を狙い撃ちにする各種控除の縮小、また消費税の税率アップについては既定方針であるかのように時期や税率まで具体化してきた。 そもそも定率減税は1999年に当時の危機的な経済情勢を救うための対策として行われたものだが、あわせて日本の社会経済構造を変革するためのステップとしても位置付けられたものであったという。だからこそ 「恒久的減税」と謳(うた)われたのであろう。 それにもかかわらず、この「恒久的」措置をわずか5年で、しかも、たいした議論もなしにあっさり葬りかねないこのたびの政府の動きと、これにあまり抵抗を示そうとしない、いわゆる有識者やメディアの有様(ありさま)を見ると、この国は一体どうなっているのだろうかと頭を抱え込まざるを得ない。 政治は言葉が基本であるというのに、国のリーダーの発する言葉や法律に信頼が置けなくなったら国民は何を頼りにしたら良いのだろう。「減税幅の縮減は増税には当たらない」 とか 「GDP(国内総生産)の1.5倍にもなる膨大な借金を返済するには増税しかない」 などと短絡的に決め付けてしまうのは、あまりにも国民を愚弄(ぐろう)した話だ。 先の選挙に際して、なぜ堂々と説明し、国民の理解と納得を得ようとしなかったのだろうか。 国民の多くは 「自分たちはこんなに多額の借金をした覚えはない!」 と思っているはずだ。為政者は 「道路や橋を作り、年金や保険の給付を受けたら、このように借金が膨張するのは当たり前だ!」 と言いたいのだろうが、そういう説明を国民は今まで一度も聞いたことがない。 一般会計の無駄遣いも会計検査院から数多く指摘されているが、わずか数パーセントを検査の対象にしただけで数百億円の無駄が指摘されている、とのことだから、全体を推測すると怖くなる。 特別会計の中身にいたっては全くの闇である。郵便貯金や年金資金がどれだけ不良債権化し実質的に目減りしているのか、全貌(ぜんぼう)を把握している政治家は果たして何人いるのだろうか。把握しようとする気概ある政治家が果たしているのだろうか。中央官庁の役人達のやりたい放題になっているのではないのだろうか。大きな混乱が予測されるので、全貌を明らかにすることができないほど事態は悪化しているのではないか、などと憶測したくなる。 年収をはるかに超える借金を背負い、返済のためにまた新たな借金をする、いわゆる自転車操業の状態はもはや瀕死(ひんし)の状態である。ひとたび、かかる状況に陥れば、よほどの幸運がなければ再起はまず不可能であり、民間企業であれば経営者は株主に対して責任を明らかにして辞任するのが当然だ。国であれ自治体であれ例外であるはずはない。 公共事業がもはや景気回復には寄与しないことを承知しながら、国民の無知を良いことに長年にわたって関係業界の要請を受け入れ、多額の借金を重ねてきた政権与党の責任は重い。 先の大戦の責任を国民自身の手で明らかにすることができなかったために、60年後の今日、国の内外にいろいろな問題を生じていることにも思いが及ぶ。わが国は責任追及が苦手であり、過ちに対してあまりに寛容過ぎる。それは個人レベルでは美徳かもしれないが、組織や集団の間では無責任体制を助長することになり、決して好ましいことではない。 財政再建の論議を起こすためには、まず為政者たちが今日の事態を招いたミスリードについて、率直に過ちを認め責任を明らかにすることが出発点である。それが 「社会の常識」 というものだ。税制論議はその後である。 もちろん今の財政状態を放置してよいなどとは誰も考えてはいない。これから迎える少子高齢化の進む成熟国家において、負担と給付の関係をどのようにするのか、という最も基本的な問題について、政府と国民の間で十分に議論され合意がなされ、合わせて累積する借金をどのようにして返していくのかについての展望が明らかにされれば、その時はじめて、国民は 「増税もやむなし」 と受け入れることになるだろう。そこには苦難もあるが希望も見いだせるのだから…。 今のような状態のまま責任もうやむやに、全貌も明らかにされぬままに圧倒的多数を占める政権与党の腕ずくで法律が改正され、給付は年ごとに減り、増税が次々と行われていくようなことになれば、国民には全く救いがない。政治が信頼を失うだけに止まらず、社会から 「常識」 や 「責任」 「信頼」 といった最も基本的な要素が失われることになりかねない。政治の要諦(ようてい)は国民に苦難の中にも信頼と希望を与え続けることではないのだろうか。 |
|